
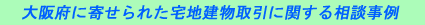
「区分所有建物の賃貸借契約において、共益費についての説明が
事実と異なっていたとして苦情が申立てられた事例」
賃貸借契約締結
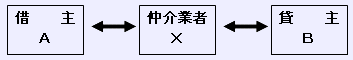
【経過】
借主Aは、宅建業者Xの媒介で、Bを貸主とするマンションの賃貸借契約(借賃月
4万円)を締結した。重要事項説明では共益費は借賃に含むと説明を受けていたが、
実際はBから共益費として借賃とは別に月5千円を請求された。
また、契約後約1年が経過しているにもかかわらず契約書の交付を受けていないと
して、Aは府に苦情を申し立てた。
【判明した違反事実】
府がXに事情を聴いたところ、以下のとおり違反事実が確認された。
1 重要事項説明書に次の記載不備がある。業法第35条第1項違反
① 当該宅地建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人
又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
(同項第1号)
・建物について、登記がされているにもかかわらず、記載していない。
② 借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的(同項第7号)
・借賃の他に月5千円の共益費がかかるにもかかわらず、借賃に含まれる旨記
載した。
・鍵代及び家賃保証会社の保証料を記載していない。
③ 契約の解除に関する事項(同項第8号)
・契約の解除に関する事項について記載していない。
④ 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項(同項第9号)
・損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について記載していない。
※なお、Xが使用していた重要事項説明書は市販されている書式であり、以下の事
項の記載欄を設けていないなど、重要事項説明書の書式として極めて不備なもので
あった。
・貸主の氏名・住所(「所有者」の欄しかない)
・造成宅地防災区域の内か否か
・土砂災害警戒区域の内か否か
・石綿使用調査の内容
・耐震診断の内容
・契約の解除に関する事項
・損害賠償額の予定及び違約金に関する事項
・支払金又は預かり金の保全措置の概要
・金銭の貸借のあっせんに関する事項
2 賃貸借契約書(いわゆる「37条書面」)をAに交付していない。
業法第37条第2項違反
【違反が発生した事情(又は理由)】
1について
Xは①及び③についてはAに口頭で説明したと述べ、①~④を重要事項説明書
に記載していないことについて不備を認めた。
また、この重要事項説明書の書式(市販のもの)を日ごろから使用していると
のことであった。
2について
Xは、契約当初にAがBとトラブルを起こしたことからBより契約書が返って
こず、渡すことができなかったと不交付を認めた。
【処分等】
府は、次のとおり違反事実等を認定し、Xを指示処分とした。
業法第35条第1項違反及び第37条第2項違反
【本事例のポイント】
重要事項説明書について
① 借賃以外に授受される金銭の額及び目的として、共益費、鍵代や家賃保証会社の
保証料などについても重要事項説明書に記載する必要があります。
|
② 市販の重要事項説明書等を使用される場合は内容に不備がないか確認する必要が
あります。
|
