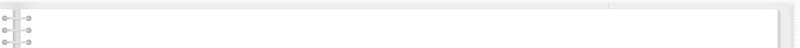
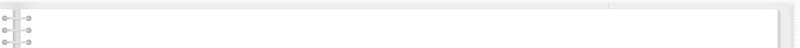 |
|
消費税事業者免税点制度の留意点 税理士 金井 恵美子 |
| 平成22年度税制改正において消費税の事業者免税点制度の改正が行われました。さらに、平成23年度税制改正においても改正が予定されており、消費税の事業者免税点制度が複雑になっています。 (1)課税事業者と免税事業者 消費税は、事業者を課税事業者と免税事業者に区分しています。平成23年度改正予定を含め、免税事業者となるかどうかの判定は、次のとおりです。
上記の判定により免税事業者とならない個人事業者及び法人は、すべて課税事業者となります 。 課税事業者は、売上げの消費税額から仕入れの消費税額を控除(この控除を仕入税額控除といいます)した残額を申告納税します。仕入れの消費税額が売上げの消費税額を上回ればその差額は還付されます。 しかし、免税事業者は、納税が免除され、還付申告を行うことができません。 (2)マンション建築費についての還付スキーム ところで、不動産貸付けを行う場合、事務所等の家賃収入は課税されますが、住宅の家賃収入は非課税売上げとされています。その課税期間の課税売上割合が95%未満の場合には、非課税売上げのための課税仕入れ(家賃収入を得るためのマンションの建築費など)は、仕入税額控除の対象になりません。しかし、課税売上割合が95%以上の場合には、すべての課税仕入れが仕入税額控除の対象となります。 近年、マンション経営を始めるにあたって、マンションの建築費に係る消費税の還付を受けるスキームが見られました。それは、課税期間の終了間際にマンションの完成引渡しを受けることによって家賃収入は翌課税期間から発生するようにしておき、完成引渡しの課税期間には自動販売機を置くなどして課税売上げを発生させ、課税売上割合を意図的に95%以上にして、本来は控除の対象にならないマンション建築費について仕入税額控除を行うというものです。還付を受けた課税期間の3年目には、その還付が適正であったかどうかの見直しを行う「調整対象固定資産に係る仕入控除税額の調整」の規定がありますが、3年目に免税事業者であれば、あるいは簡易課税制度を適用していれば、見直し規定の対象になりません。いわゆる還付逃げが可能となります。これは、法令に違反する脱税行為ではありません。ある意味、制度の不備を利用した究極の還付スキームといえるでしょう。平成22年度税制改正においては、この還付スキームを封じる改正が行われました。 (3)課税事業者の選択と「調整対象固定資産に係る仕入控除税額の調整」 上記(1)のとおり、免税事業者は還付申告ができないので、還付を受けるためには、あらかじめ課税事業者になることを選択しておく必要があります。この選択は、事業者の任意です。ただし、免税事業者・課税事業者の区分をうまく行き交って還付申告だけをとるということを防止するために、いったん課税事業者を選択すると、2年間は免税事業者に戻ることができないこととされています。また、平成22年度税制改正においては、上記(2)のスキームによる還付逃げを防止するため、原則に加えて3年間の継続適用の制度が設けられました。 課税事業者選択の手続きは、おおむね次のとおりです。
③の制限により、調整対象固定資産の仕入れ等をした場合には、3年間ないし4年間の強制適用となります。その期間は簡易課税制度を適用することもできません。したがって、仕入れ等から数えて3年目には、「調整対象固定資産に係る仕入控除税額の調整」の規定の適用を受けることになります。 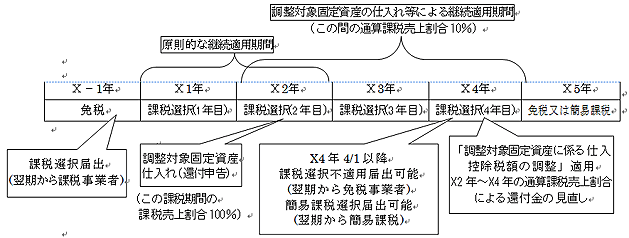
(4) 課税事業者選択の留意点 調整対象固定資産とは、建物、車両、器具備品など、有形・無形の固定資産のうちその取得が課税仕入れ等となるものであって、1個又は1組の税抜価額が100万円以上のものです。貸付け用のマンションに限りません。 免税事業者が課税事業者を選択する理由の多くは、設備投資によって生じる多額の仕入税額について還付申告を行うためです。したがって、課税事業者を選択した場合は、ほとんどのケースにおいて3年間又は4年間継続して課税事業者となり一般課税による申告を行うことになるものと考えられます。 設備投資による還付申告を目的に課税事業者を選択する場合には、次の点を考慮して、慎重に検討する必要があります。 ① 3年間ないし4年間は申告を継続しなければならないこと ② その間は簡易課税制度を適用することができないこと ③ 貸付けマンションの建築費などについて還付を受けても3年後に還付金の見直し の可能性があること ※上記は、制度の概要を示したものであるため、検討を行う際には、法令の規定をご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||
 |