
 |
|
景観法に係る最近の実例について 一級建築士 樋野 晶子 |
1 はじめに 私達建築士が建物の設計を依頼されるとまず行うことが敷地の現地調査です。周辺の状況、設備関係のインフラはどうなっているのかを詳しく調査すると共に、都市計画法、建築基準法に基づく法規制の内容をチェックし把握する事がとても重要な作業となります。この時点で少しでも見落としがあり、それに気づかず設計が進み、開発や確認申請等の申請業務時点で審査機関からの指摘を受け、設計の基本からの見直しなどという事態に至ると、依頼者に時間とコストの重大な損失を与えてしまう事にもなりかねません。 さて、建築主が土地を取得して建物を建てようと依頼される場合、思わぬ法規制がこの事前の調査で判明する事があります。そのひとつが景観法に基づく景観条例による建築物への一定の制限です(形態制限ともいいます)。景観条例とは、美しい町並み・良好な都市景観を形成し保全する為、地方自治体が制定するものです。強制力があり内容に合致しなければ建築する事ができません。景観法とはどのような法律なのかを見てみましょう。 2 景観法とは 景観法とは、2004年6月18日に公布、2005年6月1日に全面施行された、我が国初の景観に関する総合的な法律です。日本の都市、農村漁村等における良好な景観の形成を促進し、美しく風格ある国土を形成し、豊かな生活環境、活力ある地域社会の実現を図る目的で制定されました。景観法自体が直接的に景観を規制するものではありませんが、景観法に基づいて地方自治体が制定する景観に関する計画や条例、更にそれに基づいて地域住民が締結する景観協定に実効性と法的強制力を持たせようとしています。 景観計画で定める必須事項として、良好な景観形成のための行為の制限に関する事項があります。具体的には届出対象行為と景観形成基準として次のことを定めています。 ○〈届出対象行為〉 建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為など ○〈景観形成基準〉 建築物又は工作物の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限度、壁面の位置の制限又は建築物の最低敷地面積、その他景観法第十六条第一項の届出を要する行為ごとの良好な景観形成の為の制限 この景観計画を効率的かつ実効性を高めて運用する為、地方自治体は景観条例を細かく規定しています。従来の景観条例は、地方公共団体の自主条例として運用されていましたが勧告に強制力が無いなど一定の限界がありました。こうした状況を受け、法制として景観法を整備し、意義や整備・保全を国の重要課題として明確に位置付け、地方公共団体の弱点を補い、バックアップ可能な仕組みを創設し、予算や税制による支援を行うこととしたのです。 3 景観法の概要 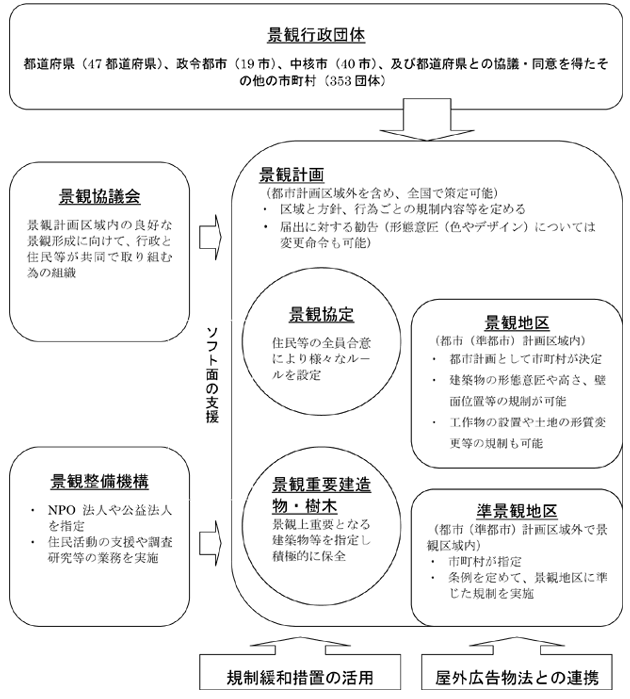 4 近畿の景観行政団体の一覧
5 景観条例による建築行為の制限の実例 私が依頼された設計・監理業務の中での実例をご紹介します。 (1)尼崎市武庫之荘4丁目での住宅の新築〜4丁目住民全員の合意による景観協定が結ばれていた例です。 この住宅の場合、「尼崎市武庫之荘4丁目地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の適用となりました。条例では、・建築物の用途制限、・建築物の高さ等の最高限度、・建築物の敷地面積の最低限度、・壁面の位置の制限などがあります。実際に建築物の高さにおいて、全体10m、軒の高さ7m制限やこの条例による敷地面積による壁面後退の制限、外壁の色も許可される範囲が限られるなどの制限を受けました。このため、建築主の要望との調整にかなり時間がかかりました。また、改装の際も届出が必要など思いがけない制限もあります。 (2)京都市上京区小島町での住宅の新築〜京都市の景観地区の指定を受けていた例です。 この住宅は、「京都市市街地景観整備条例」による「上京小川歴史的景観保全修景地区歴史的景観保全修景計画」の適用を受けました。建物を建築する承認事項として、 ・建築物の位置、・建築物の規模、・建築物の形態及び意匠などの制限があります。実際には住宅の外観について町家風の和風外観で日本瓦葺きでなければならない等様々な制限を受け建築費にも影響が及びました。また軒の出の必要寸法(30cm、60cm)の指定などがあり建蔽率以外にも土地の利用範囲が限られるといったこともありました。 また、昨年2月には兵庫県芦屋市がJR芦屋駅北の地域で大手不動産会社の5階建てマンションの建設計画を景観法に基づき建設を認めないとした例もありました。景観法を根拠に大規模建築物の建設を不認定とした全国初の例です。芦屋市は2009年に市全域を景観地区に指定、芦屋川沿いはさらに厳しい規制がかかる特別景観地区に指定されています。 6 終わりに 景観法については、今後も新たに条例を設ける市町村が増えてくるものと思われます。又、思わぬところに狭い範囲で住民の合意による景観協定がかかっている事もあります。建物を建てるために土地を取得する一般の人は、建築における専門知識に不十分なところが大いに有ります。土地の売買を経験する事は一生にそう何度もあることではありません。せっかく手に入れた土地に自分の夢である建物が、不承知であった制限によって叶えられない事は避けなければなりません。 土地の売買に携わる専門家の皆さんは、従来の都市計画法や建築基準法のみならず、近年様々な新しい、景観、環境、福祉といった私達の生活環境をより良くするための法律にも是非精通していただき、調査漏れの無いよう、又、相手方が十分に理解するよう、できれば図示などして努めて頂ければと思います。 |
 |