全国約33万地点の標準宅地の評価額の対前年変動率は、全国平均で0.2%のプラスとなり、リーマン・ショック前の2008年以来、8年ぶりに上昇に転じました。金融緩和や株高による余剰資金、海外マネーが不動産投資に流れ込んだほか、低金利が続き大都市圏などで住宅需要が堅調だったことが影響したとみられます。また、外国人観光客の増加による「インバウンド需要」も影響した一方で、大都市圏と地方の“二極化”は継続しています。
都道府県別にみると、上昇は14都道府県で、昨年より4道県増えました。上昇率は、中国人などの「爆買い」が続き、20年に五輪開催を控える東京が2.9%で最も高く、東日本大震災の復興事業が進む宮城(2.5%)、福島(2.3%)が続いています。下落は33県ですが、29県は下落率を縮小させています。
なお、全国の最高路線価は1986年から31年連続で東京・銀座中央通りにある文具店「鳩居堂」前の 銀座中央通りで32,000千円 (前年比18.7%)でした。これは、リーマン・ショック前の08年の31,840千円を超え、ピークだったバブル末期の1992年(36,500千円)の87.7に達しており、一部にはバブル再発を懸念する声も上がっています。
また、都道府県庁所在地の最高路線価をみると、上昇したのは昨年よりも4都市多い25都市となりました。大阪市北区角田町の御堂筋は22.1%上昇しており、東京23区や名古屋、訪日客が多い京都、金沢、福岡等計10都市で上昇率が10%を超えました。一方で、下落は5都市でした。大都市圏の中心部で路線価の大幅な上昇が見られる一方、それ以外の地域の大半は、下げ幅が縮小したものの下落は続いており、大都市圏と地方の二極化は依然として続いています。(【表2】参照)
なお、平成28年1月1日現在において、原子力発電所の事故に関する「帰還困難区域」、「居住制限区域」及び「避難指示解除準備区域」に設定されていた区域内にある土地等については、路線価等を定めることが困難であるため、平成27年分と同様に、相続税、贈与税の申告に当たり、その価額を「0」として差し支えないこととされています。
【表2】平成28年分都道府県庁所在都市の最高路線価
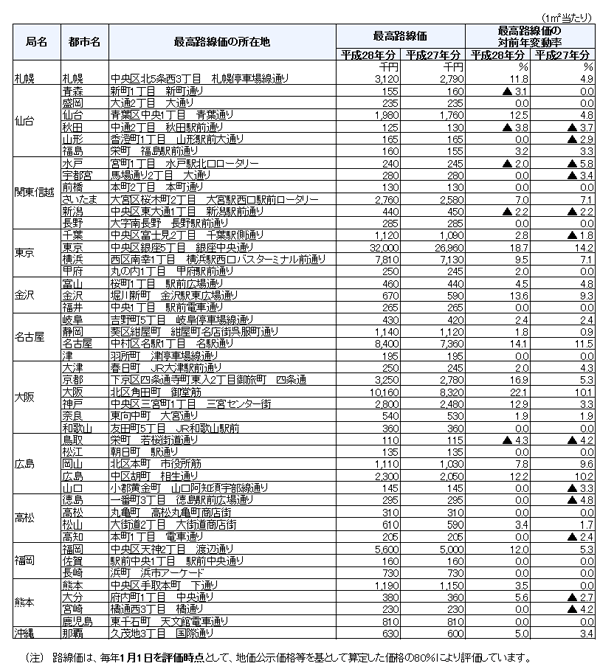
※画像をクリックすると拡大します
3. 大阪府内の地価動向 |
